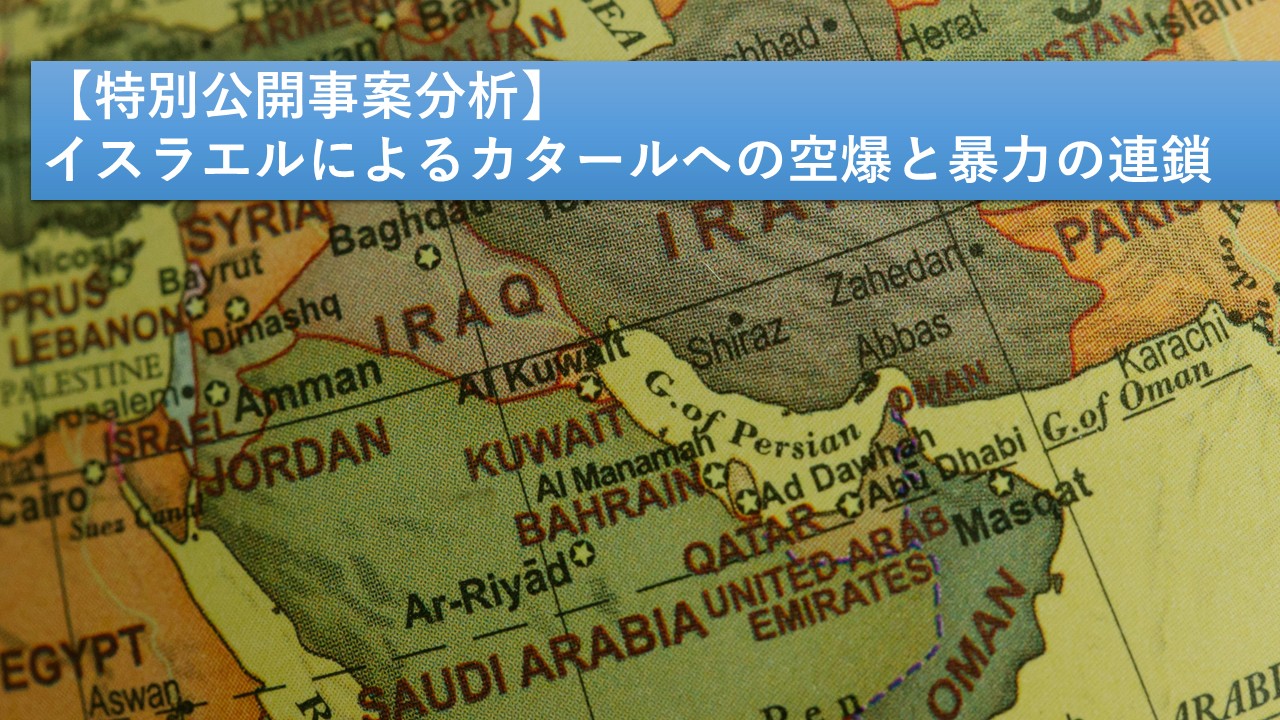2025年9月9日、イスラエルはパレスチナ武装組織ハマスの幹部が滞在していたとされるドーハ市内の住宅施設を標的に空爆を実施。この攻撃により、ハマス側は幹部の息子や秘書を含む5名が死亡したと発表し、カタール政府も自国治安部隊員1名の死亡も確認した。直接的な軍事衝突とは無関係だったカタールの首都ドーハに対し行われた正規軍による空爆は、ハマスへの報復の域を超え、中東地域の外交秩序と和平交渉の根幹を揺るがす事態へと発展している。
この空爆は、前日にエルサレム北部で発生した銃撃事件への報復とされている。ハマスの軍事部門「アル・カセム隊」に所属する2名のパレスチナ人がバス停付近で銃を乱射し、イスラエル人6名が死亡、8名が負傷した。イスラエル政府はこの事件を契機に、ハマス幹部の殺害を「正当な軍事行動」と位置づけ、カタールが主導し、米国も協力するという体制で進められていたイスラエルとハマスの停戦交渉中、というタイミングで交渉を仲介している立場のカタール首都、ドーハへの空爆を実行した。

この攻撃は国際社会において強い反発を招いた。攻撃された当事国であるカタールは「国家主権への侵害であり、外交的裏切り」と非難し、国連人権理事会は緊急討議を開催する事態に至った。事前に攻撃の通告を受けていたとの報道もあったアメリカですら「和平交渉を損なう一方的な行動」としてイスラエルを批判し、欧州連合(EU)はイスラエルの極右閣僚に対する制裁案を検討している。また欧州内では本攻撃以前にパレスチナの国家承認方針を表明していたイギリス、フランス、スペイン、アイルランド、ノルウェーに加え、本攻撃をきっかけにドイツもイスラエル寄りの姿勢を修正する方針が示されている。
カタールはこれまで、イスラエルとハマスの停戦交渉における主要な仲介国として機能してきた。ドーハにはハマスの政治指導部が長年拠点を置いていることは明らかであり、イスラエルおよびハマス双方とコミュニケーションが取れる国家としてカタールは重要な位置づけにあったと言える。今回イスラエル人人質の解放を含む和平交渉を仲介していたカタールへの突然の空爆はその交渉の信頼性を根底から崩し、カタール首相は「和平の可能性は消えた」と明言。アラブ諸国は連帯を示すため、UAE・サウジアラビア・ヨルダン等中東の主要国首脳が相次いでドーハを訪問し、イスラエルへの非難声明を発表した。
イスラエル国内でもこの作戦に対する意見は分かれている。同国内で対外的な諜報を担う情報機関モサドは地上作戦を拒否し、空爆への関与を避けたと報じられている。一方、ネタニヤフ首相は「イスラエル単独の作戦であり、国を守るために必要な措置であった」と強調し、強硬姿勢を崩していない。このような状況下で、国連における「パレスチナ国家の樹立」「二国家共存」への支持は拡大しており、米国とイスラエルの反対を押し切る形で国際世論が動き始めている。イスラエルの入植政策やガザ地区への軍事作戦により、外交的にはイスラエルが孤立しつつあるとの分析も多い。
今回のドーハ空爆は、イスラエルの対ハマス軍事戦略の延長線上にある一方で、外交的には中東秩序の再編を促す分岐点となった。今後の展開は、軍事行動と外交交渉の双方において、複数のシナリオが並行して進行する可能性がある。主たるシナリオは、現状の「にらみ合いの継続」である。ネタニヤフ政権は国内の極右勢力と連立を維持しており、政権交代の兆しは乏しい。サウジアラビアやカタールを含む湾岸諸国も、イスラエルとの全面対立を望んでいるわけではなく、外交的非難を強めつつも、軍事的報復には踏み込まない姿勢を維持している。この構図は、短期的には停戦交渉の再開を困難にし、中東和平の枠組みは「空洞化」したまま推移するだろう。
一方で、別のシナリオも浮上している。国連安保理では、カタールの主権侵害を理由にイスラエルへの制裁決議案が提出される可能性があり、欧州諸国の一部は極右閣僚への入国制限や経済制裁を検討している。ドイツがイスラエル寄りの立場を修正したことは象徴的であり、国際世論の圧力が高まれば、イスラエル国内でも軍事作戦の継続に対する疑問がさらに広がる可能性がある(イスラエル国内も一枚岩ではなく、反政府デモもしばしば発生している点に注意が必要)。また、現場ではハマス以外の武装勢力が報復を名目に越境攻撃を強化するリスクもある。レバノン南部やシリア国境地帯では、イスラエル軍とヒズボラとの小規模な衝突が再燃する兆しもあり、地域的な軍事緊張が拡大する可能性は否定できない。
こうした状況下において、ビジネス面では当面の現状維持を推奨したい。カタールを含む中東諸国の金融市場や物流拠点は安定を保っており、イスラエル国内でも経済活動は継続している。また、日・米・英・豪いずれの国もカタールに対するトラベルアドバイス上リスクレベルを引き上げた国はない。ただし、突発的・偶発的な軍事衝突の際には中東一帯の領空封鎖などを通じて日本企業のビジネス、日本人の移動にも影響を及ぼすことは言うまでもない。中東で事業展開する日本企業はもちろんのこと、中東への渡航を予定している方、また中東経由で世界各地への移動を計画する方は今後の国際情勢の推移を注視しつつ、柔軟な対応が取れるよう備えていただきたい。具体的には、飲食料品を少し多めに手元に置いておく、常備薬や生理用品などの生活必需品を余裕を持って携行するなど、日常の延長線上でできる備えが有効である。過度な警戒ではなく、冷静な準備を心がけることが、予期せぬ事態への対応力を高めることにつながる。
この項終わり